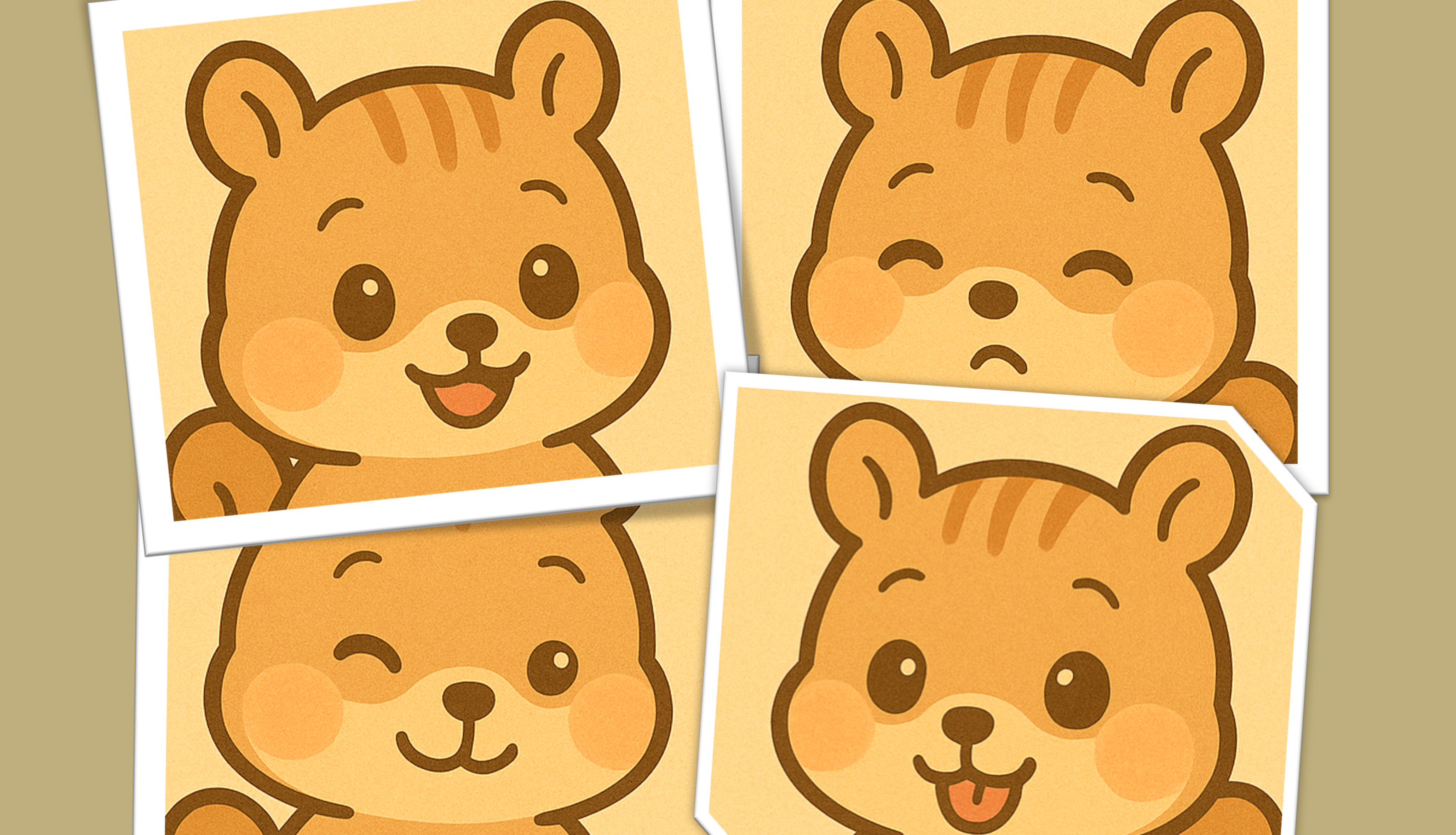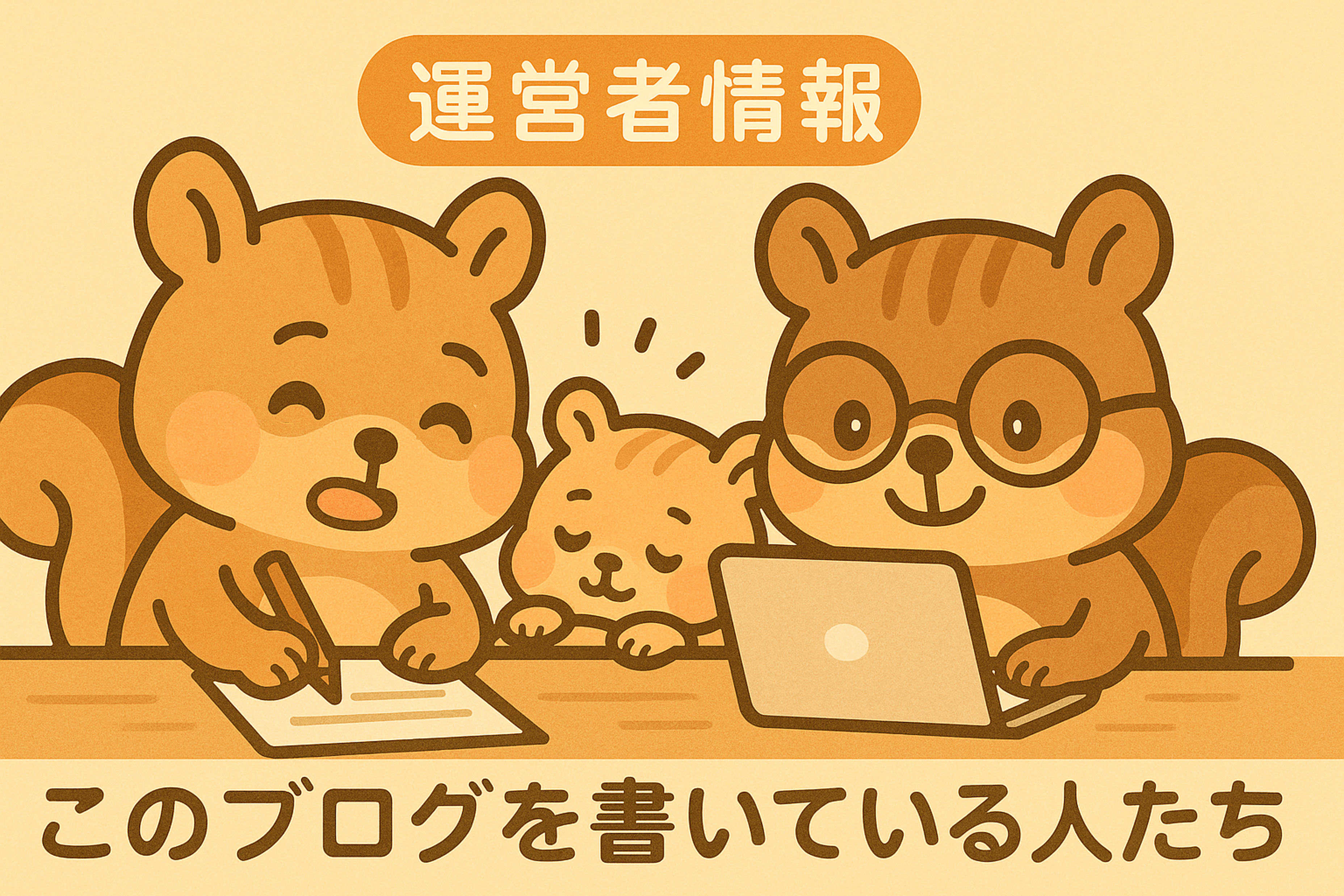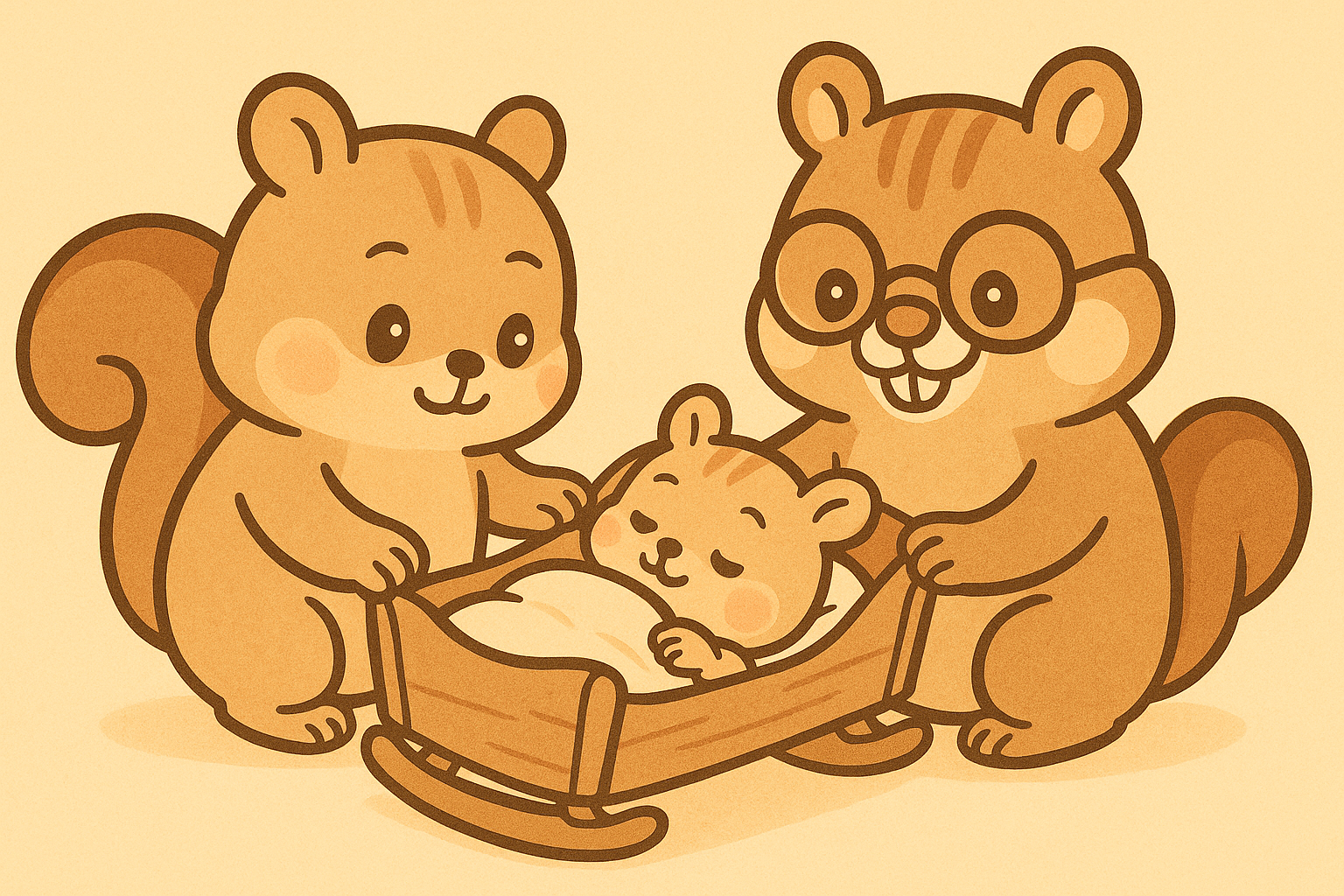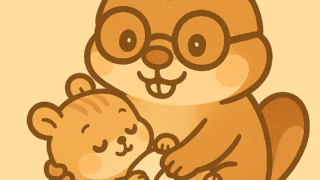こんにちは、ママぴよです。
今回は、退院間際に赤ちゃん(ふわ子)が「新生児黄疸」と言われ、予定していた里帰りをいったん見送ることになった体験と、その後の受診・日常の整え方・里帰り再開までをまとめます。これから退院を迎えるご家庭や、黄疸の経過観察で不安な方の参考になれば幸いです。
退院直前に伝えられた新生児黄疸
退院前日の血液検査で、ふわ子の総ビリルビン値(TB)が基準より高いことがわかりました。ビリルビンは赤血球が壊れる過程で生じる色素で、新生児は肝機能が未熟なため処理が追いつかず、皮膚や眼球結膜が黄色っぽく見えることがあります。多くは一過性ですが、値が高い場合は合併症のリスクを避けるため経過観察が必要になります。
この結果を受け、実家への里帰りは延期。退院後はパパビーと3人での新生活をスタートすることになりました。
退院直後の暮らし:不安と向き合う最初の数日
里帰りに頼れると思っていた分、予定変更の不安は大きく、日中は私とふわ子の2人きり。新生児の生活は「泣く→おむつ→授乳(母乳+ミルク)→睡眠」の繰り返しですが、背中スイッチや浅い眠りもあって思うように休めません。外出制限のある時期は、窓際で日向ぼっこをする程度。
授乳しても泣き止まない時は「どこが不快なのか」「病院へ連絡すべきか」など迷い、不安が募りがち。夕方、パパビーが帰宅するとホッとし、抱っこであやしてもらえるだけで心の負担が軽くなるのを感じました。
夜のルーティンと背中スイッチへの工夫
夜は3人で入浴(ベビーバス)、その後に授乳しベビーベッドへ。ところが背中スイッチで目が覚めてしまい、寝かしつけに時間がかかることもしばしば。以下の工夫で徐々に成功率が上がりました。
- 完全に深い眠りに入るまで待つ(目安20分程度)
- バスタオルごと抱っこ→そのままベッドへ(触感の変化を減らす)
- おくるみやスリーパーで包み、安心感を保つ
- 部屋の明るさと室温(環境刺激)を一定に保つ
背中スイッチは育児用語であり医学用語ではありませんが、同じ経験をする家庭は多いようです。「うちだけじゃない」と知るだけでも気持ちは少し楽になります。
初めての再診:受診準備と検査の流れ
受診日は、初の赤ちゃん連れ外出。おむつ・着替え・授乳セット・白湯や調乳用のお湯など、持ち物は事前にリスト化しておくと安心でした。待合は産婦人科の一角で、赤ちゃん連れは私だけ。泣いたらどうしようと緊張しましたが、スタッフの方が声をかけてくださり落ち着けました。
新生児診察では、体重測定・母乳量チェック・採血が進みます。結果は「母乳量は少しずつ増加」「体重は増え幅がやや控えめ」「TB値は依然基準を上回るため要観察」。5日後に再診となり、改善がなければ光線療法(光療)の可能性があると説明を受けました。
光線療法とは:特殊な青色光を照射し、ビリルビンを体外へ排出しやすい形に変化させる治療。経過や値によって入院のうえで行われることもあります。実施の要否は医師の判断に従います。
説明を聞くと緊張しますが、「次にどうなったらどうするか」が明確になると、家庭での見守り方も整理できます。
数値と気持ちの揺れ:家でできたこと/しなかったこと
再診までの間、家庭で積極的にできることは多くありません。私はできる範囲の授乳(母乳+ミルクの併用)と、こまめなおむつ替え、可能な範囲での日光浴、自分自身の休息に意識を向けました。
「数値に一喜一憂してしまう心理」は自然なものですが、困ったら相談できる先(産院・地域の子育て窓口)をメモしておくと安心材料になります。パパビーが帰宅した後の短い大人時間も、心のバランス維持に役立ちました。
再受診の結果と次の通院
緊張の再診日。検査ではTB値が基準内へ。黄疸所見はやや残るものの、医師からは「このまま様子を見て、次は1か月健診でよい」との説明があり、胸を撫で下ろしました。体重は「もう少し増やしたい」との指導があったので、授乳姿勢や哺乳びんの角度を見直し、授乳の回数と量のバランスを医師・助産師と相談しながら調整しました。
里帰りを再開:移動・環境の整え方
通院の目処が立ったため、実家への里帰りを再開。車での移動はチャイルドシートを確実に装着し、途中で休憩を入れながら向かいました。新生児期は体が小さく、固定していても揺れが気になることがあるため、出発前にベルト調整の再確認を。到着後は寝床の安全確認、調乳動線、おむつ替えスペースを整え、生活が回りやすいレイアウトを先に作っておくと、その日の夜から楽でした。
里帰り生活で感じた環境のギャップと対処
里帰りはサポートが得やすい一方、住環境と生活リズムの違いに戸惑う場面がありました。
住環境の違い
わが家は平屋で空調が均一に効くのに対し、実家は2階建て・築年数もあり、冬は冷えやすい場所が点在。調乳や消毒の動線に階段の上り下りが入ることも負担でした。
対策:2階にも簡易の授乳・調乳ステーションを作る/保温ボトルを活用/就寝前に必要物品を上階へまとめておく。
生活リズムの違い
家族は大人中心の夜時間に慣れており、テレビや会話が続くことも。私は赤ちゃん中心の静かな夜に慣れていたため、最初は落ち着かない気持ちがありました。
対策:就寝前は照明を落とし、テレビ音量を下げるなど、「赤ちゃんの夜の合図」を家族に共有。必要に応じてホワイトノイズややさしい子守唄で環境音を均すのも有効でした。
役割の持ち方
「何もしていない」と感じる罪悪感が募る日は、自分から夕食の下準備など小さな役割を引き受けると、気持ちの拠りどころに。無理のない範囲で「お願いしたいこと」「手伝えること」を可視化し、相互に声をかけ合うと、家族全体のストレスが和らぎました。
祖父母・ペットとの暮らしで気をつけた点
実家では祖父母が赤ちゃんに夢中。抱っこや哺乳びん洗いなど、人手のありがたさを実感しました。一方、室温・湿度・換気は大人の体感と差が出やすいので、温湿度計を一つ置くだけでも会話がスムーズに。
ペット(猫)とは直接接触を急がない、寝床・哺乳びん・消毒用品の置き場を完全に分けるなど、動線を区切ることで安心して共存できました。
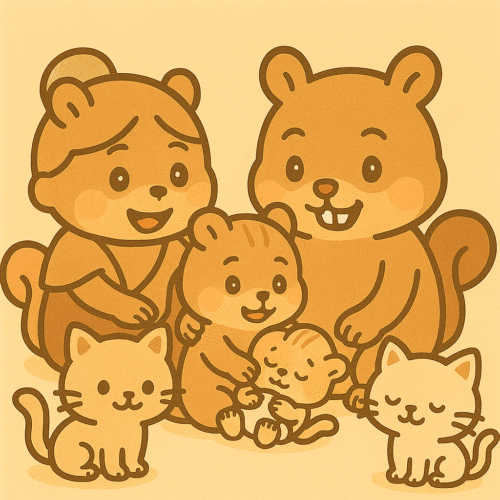
新生児黄疸:知っておきたい基礎情報(体験を踏まえた補足)
- 生理的黄疸:生後2〜3日に現れ、1〜2週間で自然に改善することが多い。
- 母乳性黄疸:母乳栄養と関連して長引く場合がある。
- 病的黄疸:値が高い・進行が速いなどの場合は、光線療法や追加検査の対象になることがある。
我が家のケースは「要観察→基準内へ」で、治療は不要でした。判断は主治医の評価と検査結果によります。家庭では、指示どおりに受診する/気になる変化をメモして伝える/親の休息を確保するのが現実的でした。
退院直後の「準備しておいてよかったもの」メモ
- 母子手帳・保険証関連・診察券(すぐ取り出せるポーチに)
- おむつ・おしりふき・ビニール袋(外出時は多めに)
- 授乳ケープ・哺乳びん・ミルク・保温ボトル(調乳動線の短縮)
- ガーゼ・タオル・着替え(背中スイッチ対策にバスタオルも便利)
- 温湿度計・小型加湿器(環境の見える化)
- チェックリスト(受診前日のうちに確認)
振り返り:数値と生活、どちらも「伴走」が大切
退院直後は、検査数値に気持ちが揺れやすく、生活リズムも整いません。それでも、夫であるパパビーや家族・医療者と情報を共有し、できる範囲で役割を分担することで、少しずつ道筋が見えてきました。
里帰り再開後も、住環境や生活リズムに差があるのは自然なこと。言いにくいことほど「見える化」(温湿度・就寝の合図・家事役割)し、お願いと感謝をセットで伝えると、家族みんなが動きやすくなります。
何より、赤ちゃんと過ごす毎日は同じようでいて少しずつ前進しています。寝顔や小さな成長のサインに目を向けることが、親の心の回復にもつながりました。
まとめ(体験からの学び)
- 新生児黄疸は珍しくないが、数値が高いときは定期的な受診と医師の指示に沿って経過観察する
- 退院直後は母乳とミルクの併用・背中スイッチ対策・親の休息確保が現実的なポイント
- 初めての赤ちゃん連れ受診は持ち物リスト化で負担が軽くなる
- 里帰り再開時は住環境・生活リズムの違いを前提に、動線と役割の見直しを
- 数値に揺れるときこそ、相談先の確保・パートナーとの分担が支えになる
退院直後の数週間は、試行錯誤の連続でした。それでも、ふわ子と一緒に少しずつ慣れていき、気づけば家族のペースができていました。この記録が、どこかのご家庭の安心材料になりますように。
※本記事は個人の体験談です。診断や治療の判断は医療機関の指示に従ってください。体調や様子に不安がある場合は、早めにかかりつけへ相談を。
ママぴよ
▶ まとめ記事から選んでもう一度読む:無痛分娩と産後生活の6つの体験談まとめページはこちら
▶ 次に読む:パパの抱っこがラクになる工夫2選|筋トレ×癒しルーティンで乗り切る育児術!