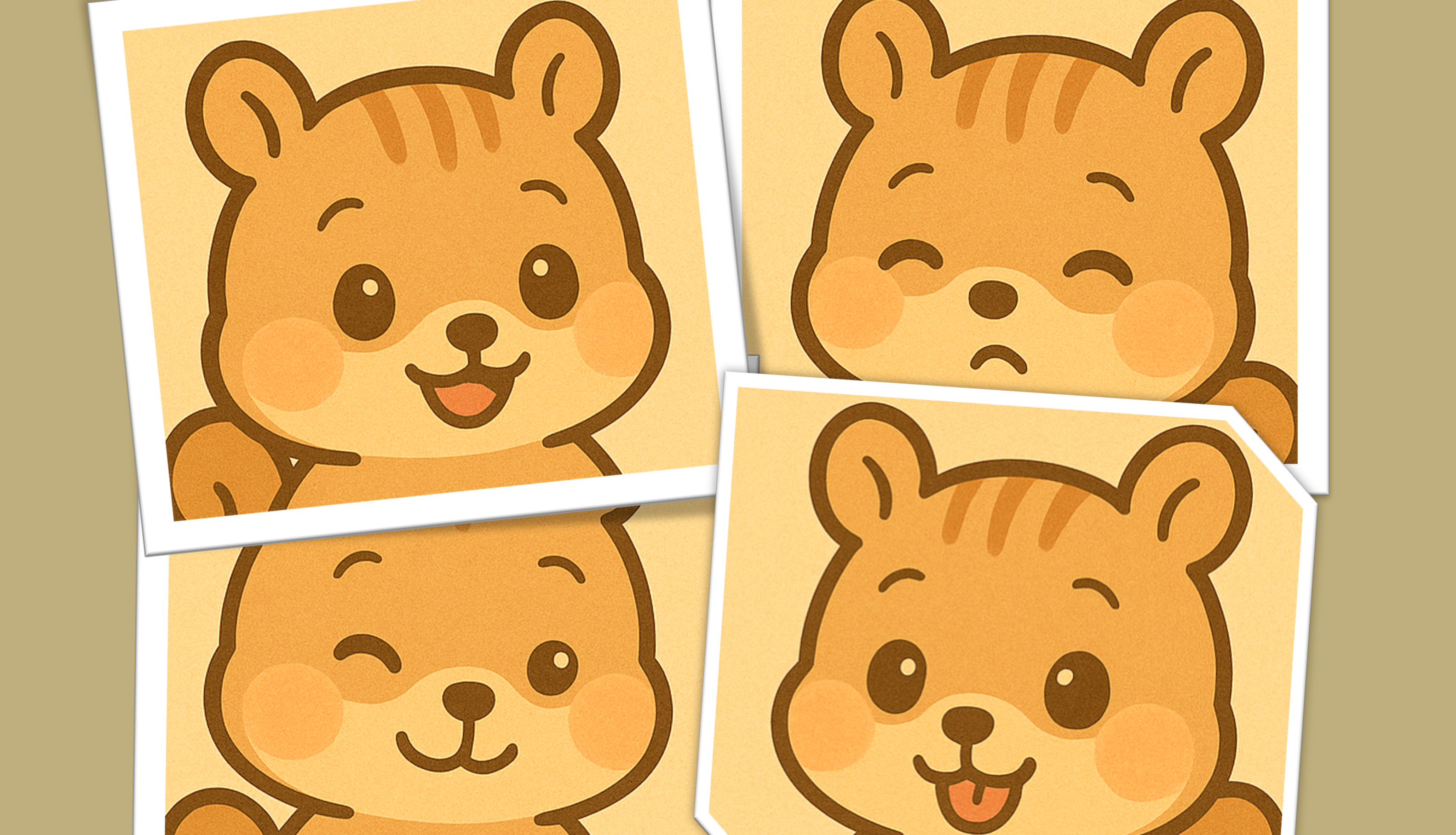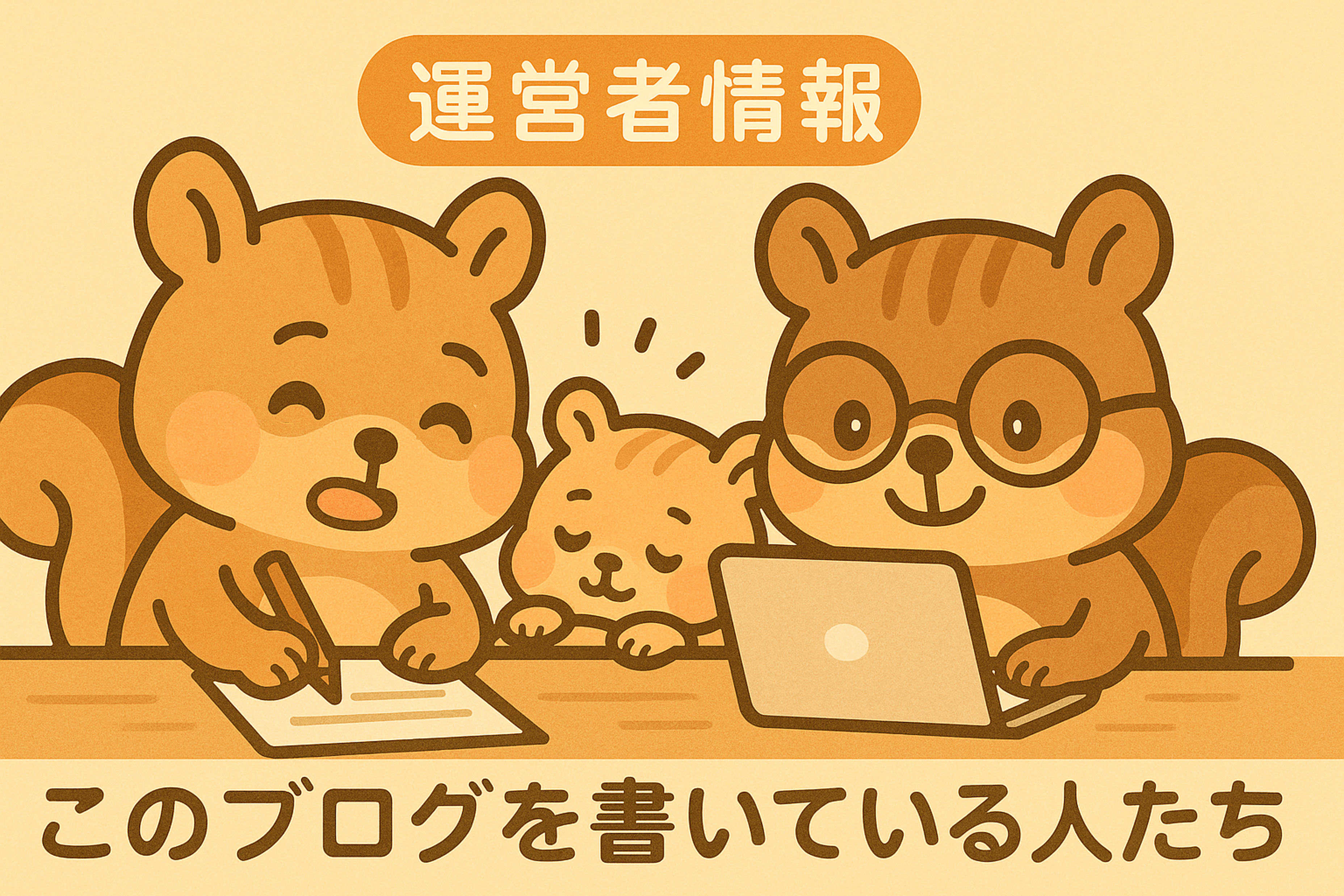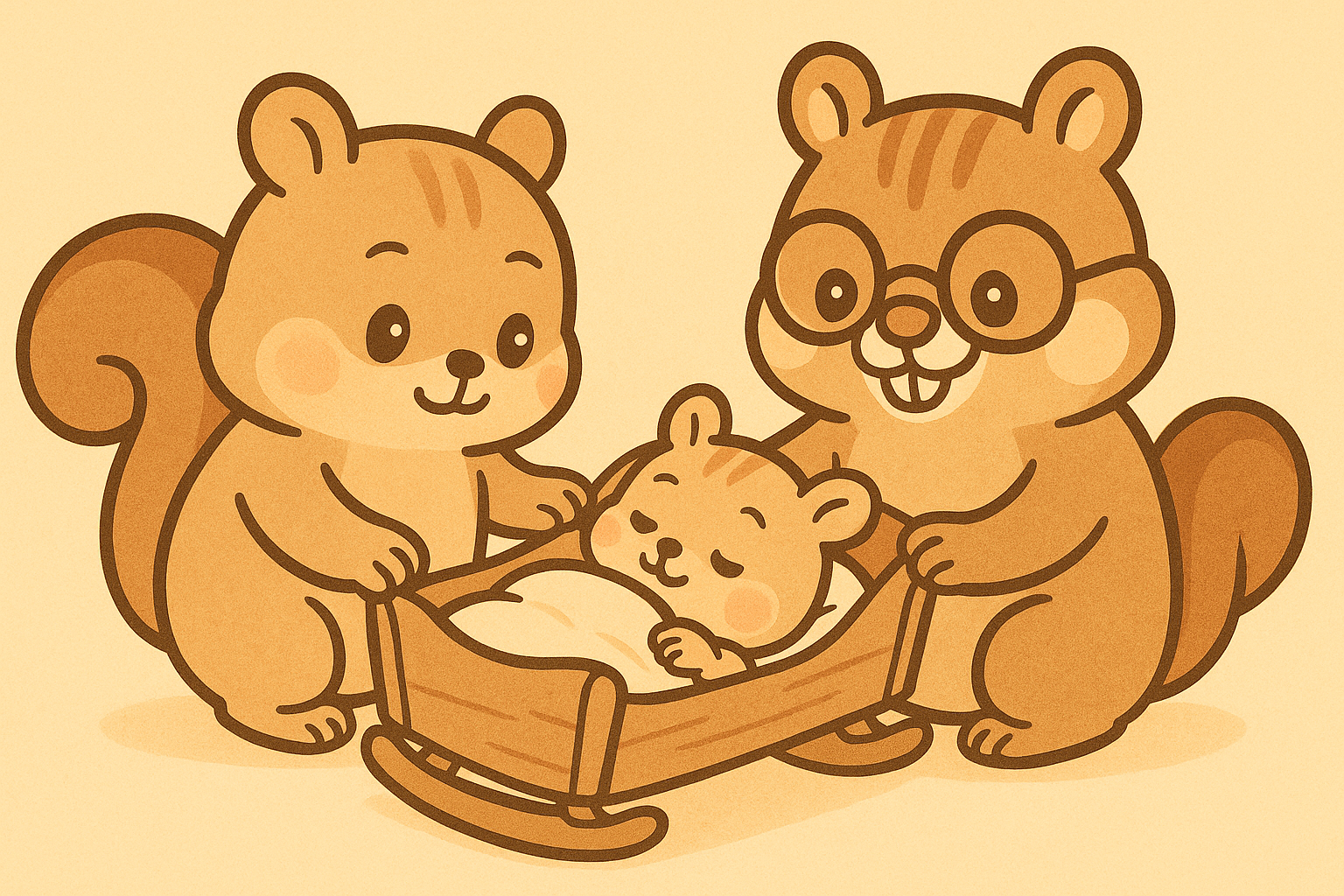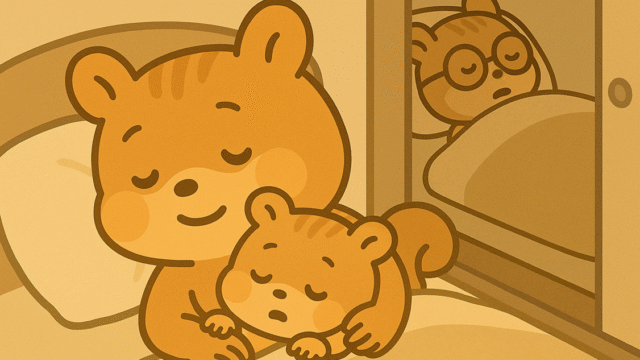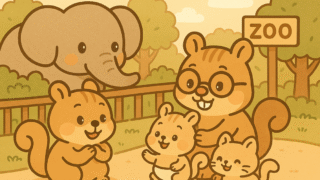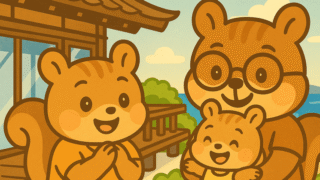こんにちは。パパビーです。
昔の同級生が「ゲームは楽しいけど、時間かけても何も残らないからなー」と大人になってから言っていたのが、ずっと心に残っていました。
漠然と「実質的に残るものは無いかもしれないけれど、本当に何も残らなかったのかなぁ?」と疑問に思ったので、このエピソードを覚えているのかもしれません。
代表作、星のカービィやスマブラで知られる、有名なゲームクリエイターの桜井政博さんのYouTube動画で印象に残ったセリフがあり、この疑問への自分の答えがでたことと、子育てにも活かせそうだと思ったので書いてみます。
ゲームクリエイター界の生ける伝説 桜井政博
過言ではなく、桜井さんはゲーム業界の生ける伝説です。
下記のYouTube動画は全て桜井さんのボランティアの賜物で、広告掲載も無いのですが、
1億円弱の総製作費がかかっているそうです。
パパビーは初代カービィ・カービィ2・夢の泉・スパデラ・スマブラと軒並み桜井作品をプレイしていることもあり、更にこの動画もあって彼のファンです。
桜井政博さんのゲーム作るには_収納のしかた【雑談】
※スタート位置を調整していますが、シリーズ通してとても面白いので気になる方は是非最初から視聴してみてください;)
シリーズ最後の動画で大きな秘密が明かされるのも必見です!
ちなみにこの動画でリプレイ回数が最も多い部分は、猫のふくらしさん登場シーンです:D
たくさんのゲームソフトを収集している桜井さんですが、近年のソフト購入にはダウンロード販売を利用していると話された後の、9:12からのセリフを引用します。
モノ(ここではソフトウェア)が残ること自体の執着はあまり無いのですが
それぞれ(の作品)をプレイした経験や記憶は大事ですね。
いずれも過去に触れたり楽しんだものですから。
プレイヤーとして、そしてクリエイターとしての両方の立場から上記の太字のセリフを言っていると推測できます。
短くまとめると、
“過去に楽しんだのだから、そのゲームで遊んだ経験と記憶は大事です”
当たり前のことのようですが、パパビーにはすごく心に響きました。
楽しかった経験と記憶は大事
ゲーム要素を取り除いても、上記は人生における不変の真理だと思います。
パパビーは楽しかった経験と記憶だけで、ごはん山盛り3杯はいけます。
子どもが夢中になってゲームをしていると、親として「またゲームばっかりして……」「勉強した方がいいんじゃない?」とつい言いたくなるものです。
パパビー自身も親になって、その気持ちがよくわかるようになりました。親が「勉強しろ」と言うのは、単に点数や受験のためだけではなく、将来の“生きる力”や“稼ぐ力”を身につけてほしいという願いが込められているのだと思います。
一方で、子どもからすれば「人生を生きる力の養成ばかりに注力させられる」のは窮屈です。大人だってそうですよね。仕事や勉強だけで一日を埋め尽くされるのは嫌ですし、息抜きや楽しみがあるからこそ頑張れるのではないでしょうか。
そして「ゲーム」は、その楽しみの一つとして、単なる時間の浪費ではなく、思いがけないメリットをもたらすことが、近年の研究で明らかになっています。
親世代が抱く「ゲームは無駄」というイメージ
パパビー自身、子どもの頃に「ゲームなんてしてないで勉強しなさい」と親から言われていました。きっと多くの方も同じ経験があるはずです。
確かに、ゲームは目に見える成果や資格を残すわけではありません。パパビーの同級生のようにゲームが終われば「何も残らない」と感じる人もいるでしょう。
でも、楽しかった経験と記憶が残っていますね
思い返すと、パパビーは努力値調整した『ポケモン』で対戦するときの緊張感や手に汗握る感覚を今でも鮮明に覚えていますし、『クロノトリガー』の音楽を聴けば、当時のワクワクした気持ちがよみがえりますし、今でも時々聞いています。
ソフトウェア自体はもう手元になくても、体験や記憶は確実に自分の中に残っているのです。
冒頭で引用したように桜井さんが「ソフトウェアを残したい執着はないが、過去に楽しんだのだから、そのゲームで遊んだ経験と記憶は大事」と語っており、これは、パパビー以外にも多くのプレイヤーが共感する言葉ではないでしょうか。
例外的に、パパビーはRPGのシナリオはすっかり忘れてしまうタイプですが…
科学的に見た「ゲームのメリット」
「でも思い出だけでしょ?」と思うかもしれません。
ところが、最近はゲームが脳や心に与える良い影響がエビデンスとして積み重なってきています。いくつか研究を紹介します。
- 認知機能の向上 引用元の文献はこちら
2000人規模の子どもを対象にした研究では、1日3時間以上ゲームをする子どもは、衝動を抑える力や作業記憶が向上していたことがわかりました(米国NIHの研究)。
アクションゲームで視覚的な注意力が鍛えられる実験結果もあり、単なる遊び以上のトレーニング効果があるとされています。 - ウェルビーイング(幸福感)の向上 引用元の文献はこちら
大阪大学の調査では、ゲームがメンタルヘルスを改善し、人生満足度を高める因果関係が確認されました。
また、世界12カ国の調査では71%のプレイヤーが「ストレス軽減に役立つ」と回答しており、気分をリセットする有効な方法といえます。 - 感情体験と爽快感 引用元の文献はこちら
短時間のプレイでも「緊張」や「興奮」と同時に「爽快感」が高まることが大学生を対象にした実験で示されています。
子どもにとっても、失敗して悔しい、勝って嬉しいといった感情体験は人生の縮図のような学びにつながります。
勉強とゲームは対立するものではない
ここで大事なのは、ゲームと勉強を“ゼロサム”で考えないことです。
ゼロサム:一方が利益を得ると他方が同じだけ損失をする関係性
確かに、ゲームのしすぎで睡眠や勉強が削られるのは問題です。時間のルールを守ることは重要です。
しかし「ゲームは全部無駄」と切り捨てるのは浅はかです。
むしろ、親が子どもの興奮や楽しみを理解しつつ、「楽しいからこそルールを守る」方向へ導くのが現実的ではないでしょうか。
ゲームで得られる記憶や体験は、大人になってからも心に残ります。音楽や物語、勝負の緊張感、仲間との協力——それらはただの暇つぶし以上の価値があるのです。
親としての向き合い方の提案
パパビー自身も親になって考えるのは、「ゲーム禁止」ではなく「どう付き合うか」です。
次のような視点を意識すると良いと思います。
- 時間のルールは共有する
平日は30分、休日は1時間など、目安を一緒に決めて守る。ただし少しオーバーしても「今日は楽しかったね」と受け止める余裕も大切。子供も楽しい経験ができたのなら良いじゃない。 - プレイを共有する
子どもがハマっているゲームの内容を聞いたり、一緒に遊んだりする。親子で話題を共有できるのは貴重なコミュニケーションです。 - 学びや体験を見つける
「どうしてその戦略にしたの?」「あの音楽いいね」「パパビーのニョロボンに勝てそう?」と、ゲームの中から考えや感性を引き出す。これが“生きる力”の一部になるのです。
まとめ:ゲーム体験を人生の糧に
「ゲームなんて時間の無駄」というのは、もう過去の固定観念かもしれません。
科学的には、認知機能やメンタル、幸福感を高める効果が証明されつつあります。
そして何より、自分が子どもの頃に味わった楽しさや興奮が今でも心に残っているように、子どもたちにとってもゲームはかけがえのない思い出になります。
もちろん、勉強や生活習慣とのバランスは大事です。でも少しくらい時間をオーバーしても、「今日も楽しくてよかった」と前向きに捉えることが、子どものウェルビーイング(幸福)を育む一歩になるのではないでしょうか。
パパビー