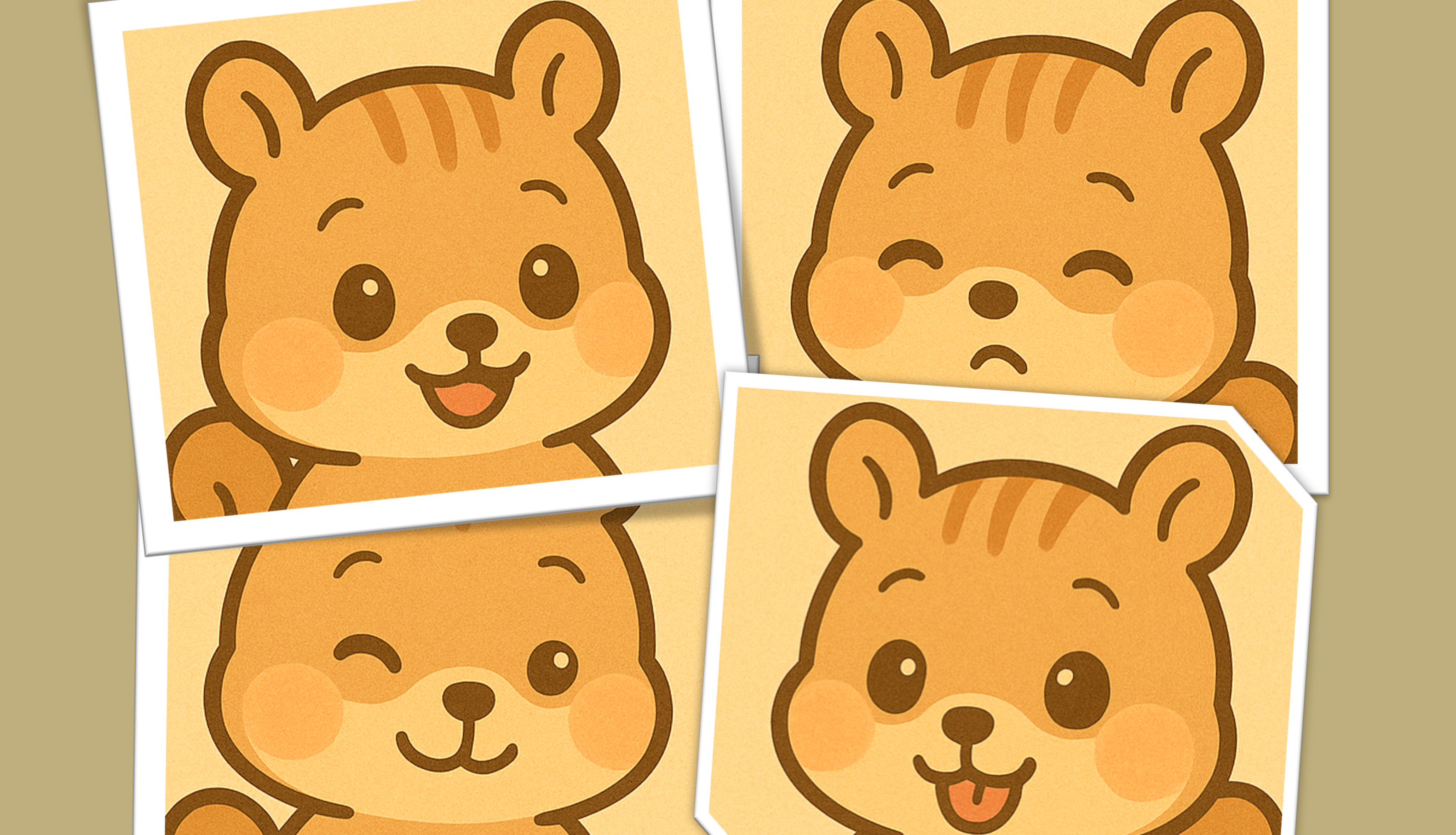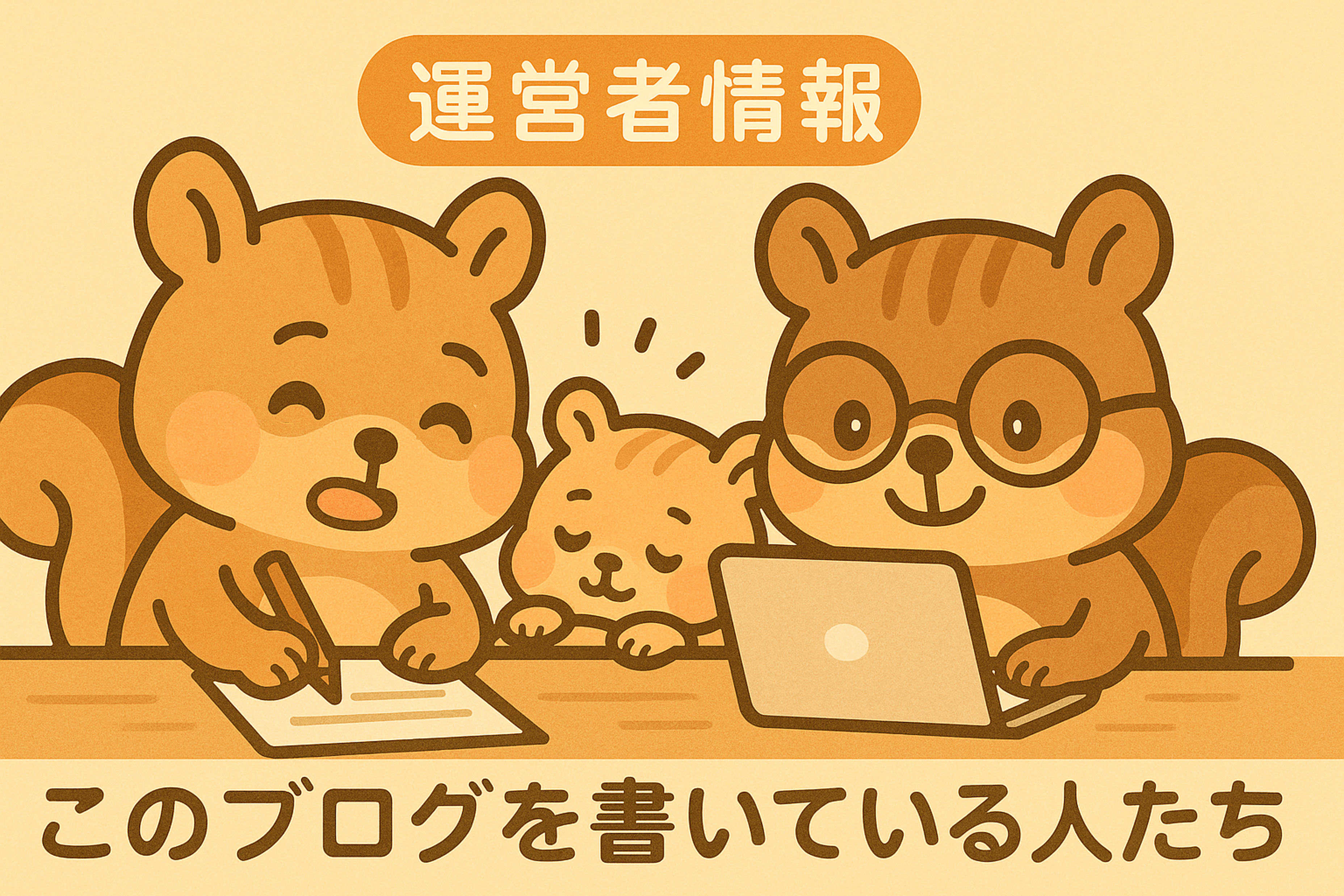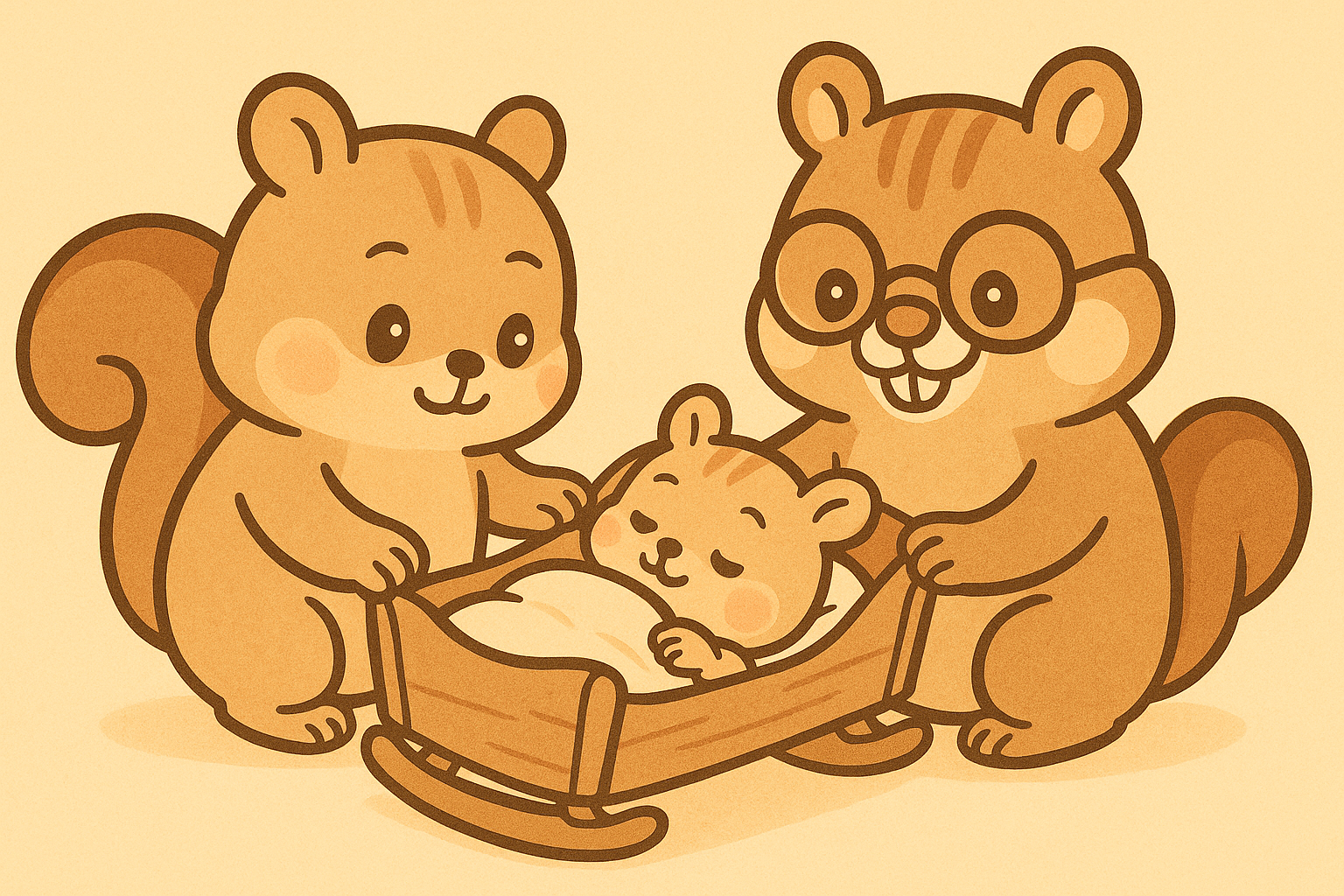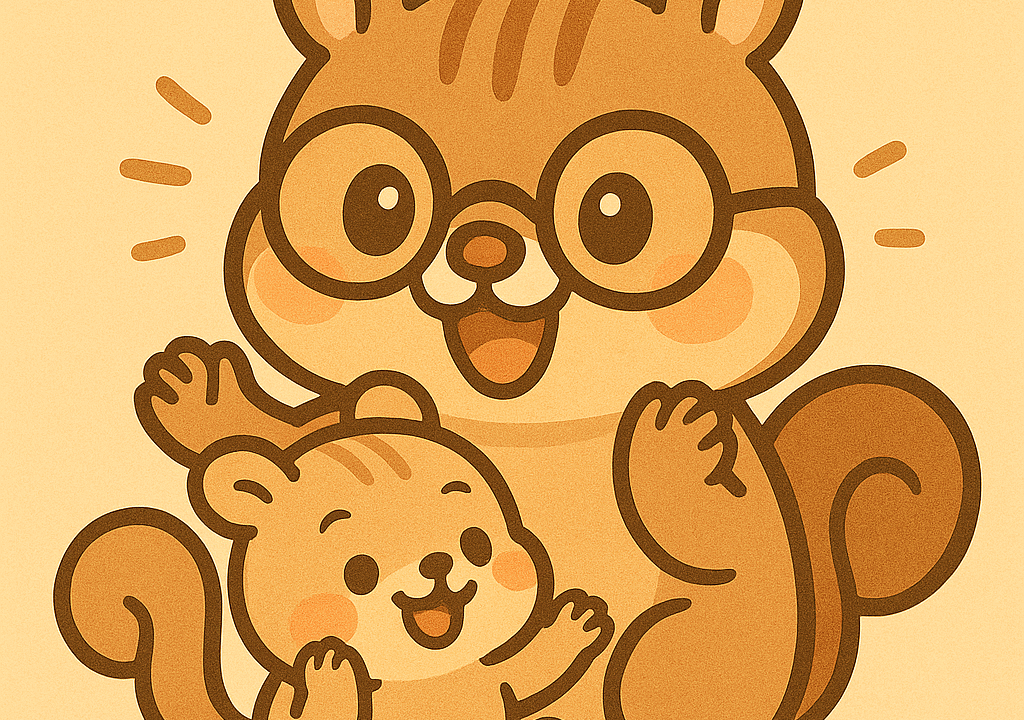パパビーです。
今回は、父親である僕自身が、子育てをする中で大切にしている「怒る」と「叱る」の違い、そしてそれをどう使い分けているかについてお話ししたいと思います。
この記事を書いている時点のふわ子は2歳半くらいです。
「怒る」と「叱る」は、似ていて違う
子育てをしていると、思い通りにいかないこと、子どもが予想外の行動をすることに直面する場面は日常茶飯事です。
そんな中で僕が意識しているのは、「怒る」と「叱る」は違うということです。
「怒る」とは、自分の感情が先に立って発する反応。イライラや苛立ちから思わず声を荒げてしまうこともあります。
一方で「叱る」は、子どもに伝えたい意図があり、何がいけなかったかを教える行為です。
僕はできる限り「怒らない」育児を心がけています。
もちろん人間なので、感情がゼロというわけにはいきませんが、「今これは怒ってるんじゃなくて、叱っているのか?」と自問しながら言葉を選ぶようにしています。
叱ると決めている「わが家のルール」
じゃあ、何でもかんでも穏やかに「ダメだよ〜」で済ませているのかと言えば、そんなことはありません。
我が家では「叱るべき場面」は、あらかじめ夫婦である程度すり合わせています。
具体的には、以下のような行動です。
- 食べ物を投げたとき
- 他人を殴ったり叩いたとき
- 命に関わる危険な行動(道路に急に飛び出す、火や刃物に触ろうとする)をとったとき
これらは、親の価値観というよりも、社会で生きる上で必要な“基本のマナー”や“安全意識”だと考えています。
そのため、「これは絶対にダメ」というラインはブレないようにしようと心がけています。
叱るには“準備”が必要?
面白いことに、叱るという行為は“準備していないとできない”という側面があります。
たとえば突然ふわ子が何かを投げたとき、「これは叱るべきか?それともまだ理解してない年齢か?」と一瞬で判断しなければなりません。
その瞬間に自分の中で基準がぶれていると、注意の仕方も曖昧になります。
だからこそ、事前に「何を叱るのか」を自分の中で明確にしておく必要があるのです。
2歳半、言葉の理解が進んでいるからこそ
現在ふわ子は2歳半。おしゃべりが大好きで、保育士さんからも「言葉の発達が早いですね」と言ってもらえるくらい、よくしゃべります。
ママぴよの実家に行った時などは、初めて会う来客などが無い限り、ずーっと喋っています。
そんなふわ子だからこそ、僕は“叱るとき”にもできるだけ「なぜそれがダメなのか」を説明するようにしています。
たとえば「食べ物を投げたらママが悲しいよ」とか「道路に出たら車が来てとても危ないんだよ」と、できるだけ具体的に。
するとふわ子も「ママかなしいの?」「くるま、こわいね」と、自分なりに言葉にして返してくれます。
もちろん、その理解が本質的なものかは分かりません。でも、小さな心で“何か”を感じ取ってくれていることは、間違いないと感じます。
怒らなさすぎるリスクもある?
一方で、最近ふと思うことがあります。
それは、もし親がまったく感情的に怒らなかったら、子どもは「他人の怒りの感情に鈍感になってしまうのでは?」という懸念です。
つまり、「何が人を傷つけるのか」「なぜ相手が不快になるのか」といった“感情の機微”を、体感として理解できずに育ってしまうリスクがあるのではないかと。
人間関係においては、“理屈だけでは伝わらない感情のやりとり”が重要になる場面も少なくありません。
もちろん、怒鳴るような育児を推奨するつもりはありませんが、あまりにも「理性的すぎる」育児も、どこか偏りを生む可能性がある。
今はそんな“揺れ”の中で、模索しながら子育てをしています。
正解はない、でも毎回振り返る
子育てに正解がないのは、頭では分かっています。
それでも、「あのときの接し方は良かったのか」「怒らずに済ませてよかったのか、それとも甘かったのか」など、日々自分なりに反省しています。
ふわ子の行動に対して自分の感情が動いたときこそ、冷静に振り返るチャンス。
感情的に反応してしまったなら、「なぜそうなったのか?」を考え直し、次に活かすようにしています。
子育てで意識しているのは「怒る」と「叱る」の違い。怒る=感情的反応、叱る=意図をもって伝える行為。
叱る対象は夫婦でルール化(食べ物を投げる・人を叩く・危険行動など)。
叱る際は「なぜダメか」を具体的に説明し、子どもも言葉で反応。
感情を全く見せないと他人の怒りを理解できないリスクも意識。
正解はないが、毎回振り返りながら模索している。
おわりに
父親として、子育てに関わる時間は、母親に比べると限られているかもしれません。
それでも、僕なりに「父親としてできること」「パパとしての関わり方」を模索しながら、ふわ子との時間を大切にしています。
怒るでもなく、甘やかすでもない。
そのちょうどよい「しつけ」の加減を探す旅は、まだまだ続きそうです。
パパビー